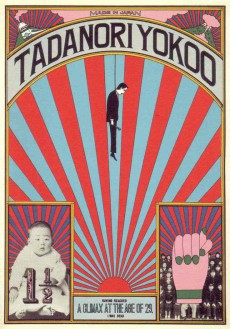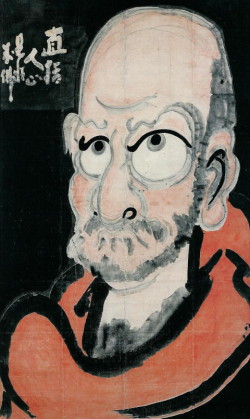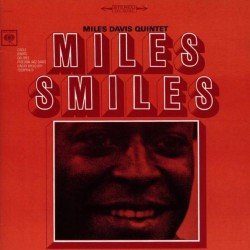20年ぶりのBand Of Pleasure
 1/14(木)~16(土)の3日間、青山のBlue Noteで、20年ぶりの同窓会 Live!メンバーは、David T. Walker(g)、James Gadson(ds)、山岸潤史(g)、清水興(e-b)と私の日米混成バンド。本当に感無量でした。去年(2015)、2/5にMarlena Shawの「“Who Is This Bitch Anyway?” リユニオン・ツアー」@高松に、危うくキーボーディストのトラ(代役)を務める羽目になりかけた椿事がありました。(詳しくは→拙記事「Who Is This Bitch Anyway?」)その時、ツアーに参加していたDavidと再会し、ゆっくり話す時間があったので、バンプレのリユニオンをしたいねと、持ちかけたら、「随分時間が経ってるけど、ジュンや、コー、ギャドもやりたい気持ちがあるかなあ?」と訊ねられ、「120%やりたいに決まってるよ。」「うん、それならL.A.に帰ったら、ジュンに電話して、皆にも連絡してみよう。」そして昔の事、今の事等々、話が咲きました。振り返ると、これがきっかけとなって、Davidがリユニオンに向けて、俄然やる気を起こしたのかなあと思います。(縁は異なもの‥‥、What A Difference A Day Made‥‥)
1/14(木)~16(土)の3日間、青山のBlue Noteで、20年ぶりの同窓会 Live!メンバーは、David T. Walker(g)、James Gadson(ds)、山岸潤史(g)、清水興(e-b)と私の日米混成バンド。本当に感無量でした。去年(2015)、2/5にMarlena Shawの「“Who Is This Bitch Anyway?” リユニオン・ツアー」@高松に、危うくキーボーディストのトラ(代役)を務める羽目になりかけた椿事がありました。(詳しくは→拙記事「Who Is This Bitch Anyway?」)その時、ツアーに参加していたDavidと再会し、ゆっくり話す時間があったので、バンプレのリユニオンをしたいねと、持ちかけたら、「随分時間が経ってるけど、ジュンや、コー、ギャドもやりたい気持ちがあるかなあ?」と訊ねられ、「120%やりたいに決まってるよ。」「うん、それならL.A.に帰ったら、ジュンに電話して、皆にも連絡してみよう。」そして昔の事、今の事等々、話が咲きました。振り返ると、これがきっかけとなって、Davidがリユニオンに向けて、俄然やる気を起こしたのかなあと思います。(縁は異なもの‥‥、What A Difference A Day Made‥‥)
20年も経ってしまったのかと思うと、月日の重みを感じますが、公演前日のリハーサルで皆と顔を合わせた途端、体が覚えている、このバンド特有の空気が戻ってきて、私の中の20年の隔たりがとけてしまいました。
このバンドの5人は、昔からそれぞれの人柄が思い切りリアルに出てくる取り合わせで、人間的性格や音楽家気質も違うのに、こと、一緒に音を出すと、自然にうまくいってしまうマジックが働くのです。その曲の最低限の約束ごとの他は、お互いに対して、特に何かを要求するということはほとんどなく、皆の出す音を聴きながら、それぞれが、自分らしいことをやれば、そのままバンプレの音になってしまうのです。不思議としか言いようがありません。ともあれ、Davidも、Gadsonもアメリカ人には珍しく、天然物の「人見知りのはにかみ屋」さん。何となく、照れくさい雰囲気もあり、ステージ付きのPAエンジニアーによると、リハーサルから日にちを重ねるにつれて、「お互いをじっくり確かめ合いながら、よりを戻していくようなリアルな感じが伝わってきた。」そうです。そんな、人間的な要素も含めて、どこを切ってもバンプレそのものの3日間でした。 夢見心地の至福の3日間もあっという間、最終日最後のセット、最後の曲”You Are My Sunshine”も、そしてアンコールも終り、ステージから下りて、いよいよ楽屋口から一歩入ったところで、山岸に「名残惜しいなあ~〜」とつぶやいたら、彼も「うん、名残惜しいわ~〜」と。それで、自然に「やっぱり、もう一曲やっとこ」と、他の皆の背中を押してステージに引き返し、「Best Thing That Ever Happend To Me、今の気持ち、これやわ」とアンコールのアンコールとなりました。
夢見心地の至福の3日間もあっという間、最終日最後のセット、最後の曲”You Are My Sunshine”も、そしてアンコールも終り、ステージから下りて、いよいよ楽屋口から一歩入ったところで、山岸に「名残惜しいなあ~〜」とつぶやいたら、彼も「うん、名残惜しいわ~〜」と。それで、自然に「やっぱり、もう一曲やっとこ」と、他の皆の背中を押してステージに引き返し、「Best Thing That Ever Happend To Me、今の気持ち、これやわ」とアンコールのアンコールとなりました。
今回は東京のみのLiveとなり、大阪や沖縄、遠くから駆けつけて下さったファンも少なくありません。客席をみると、懐かしい顔があちこちに、そして、その顔に20年の年輪が刻まれていました。ステージも客席も渾然一体となり、会場全体が20年ぶりの同窓会となりました。皆さんの温かい声援が、いまも心に響いています。有難うございました。
バンプレで演奏する、またの日がありますように!
関連リンク:Reunion 3days Liveレポート&バンプレ・ヒストリー/David T.公式サイトの記事
「バンプレそしてDavid T.のこと」(拙記事)
Band Of Pleasureの旧譜が、iTunes Storeでリリースされています。(→iTune Store)